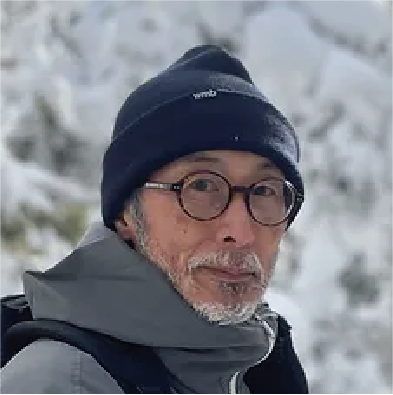
森に済みたい!
私の八ガ岳移住計画その1
土地を見つけるまで
長野県諏訪郡富士見町在住
2022年9月から茅野市に仮住まいしながら家造り中です。
切り倒した木を自宅の建材に使う予定です。
●このマンションを売って引っ越そう!
『ここで一生暮らすよりも、雇用延長が終われば、通勤の束縛からは離れるし、……』
これが始まりでした。2020年末くらいから家を売却することと次なる生活の場を探すことを並行して始めました。移住して家を建てて住み始めるまでの顛末を連載したいと思いますのでお付き合いください。
●森に住もう!
どちらかというと妻の方の思いが強かったかも。
住まうエリアとしては海より山。できれば今までもやっていた登山に行きやすいところがいい。
そして妻の仕事の陶芸が続けられるところ。
ということで長野県の中央高速沿いのエリアを探すことにしました。
始めに考えていたのは、森と言っても里山のふもとで人里と自然が接する所に古民家を買ってリフォームして住もうかという事でした。
しかし、いざ探し始めてみると安価な古民家はあるものの、古民家的姿を守りつつ快適に住うとなるとリフォームに費やす費用はただならぬものだという事が分かったのでした。それから一瞬目が眩む「広い庭がついています、畑もついています」というやつ。広すぎる庭の植木をどうすればいいんだ?起きっぱなしのガラクタを処分しなきゃ住めないじゃないか!畑と言っても家のそばじゃないし、広すぎて家庭菜園のレベルからは完全に解離していて手が出せるものじゃない!という事が現場を見て実感できました。
もしもこれから「古民家を改装して……」と思われている方、それなりの財力と住まってゆくための体力が必要なことをお知りおき下さい。
次に検討したのは、中古の別荘です。
この頃になると住みたいエリアも絞れてきて、八ヶ岳の南西のエリアになってきました。
売りに出ている物件も結構あるものの、古すぎるのは論外として、下水がなくて浄化槽だったり、妻の陶芸工房を作りたいのに敷地内に勝手に建屋を作れないという規則があったりして、別荘地の管理体制にもよりますが色々と制約が多い事がわかりました。そして何よりも「森に住みたい」という自分たちの想いに対して、森という自然環境はあるものの、そこにいるのは都会から一時的に泊まりにきているその土地とは縁のない人達なわけで、想いが満たされるものではありませんでした。
そうやって住まう場所探しに右往左往していたところ、森を切り開いて住んでいる妻の友人のそのまた友人と知り合う事ができて、ようやく森の中に住むことが実感できるようになりました。地元の土地に詳しい人の紹介や移住者向けの不動産サイトや口コミなどなどを頼りに土地を探しまくった末に、イメージ通りの土地にたどり着く事が出来ました。
エリアとしては長野県諏訪郡、八ヶ岳を北に見つつ甲斐駒を南に仰ぐところです。
縄文時代から人の営みがなされてきた場所だけあって、気持ちの良い土地です。
●土地を作ろう!
森に住むにあたって考えたコンセプトは、「地に住まわせてもらう」ということです。
細かく記すと以下のことです。
・自分たちで森の木を切って土地を作る
・切った木を使って家を作る
・基礎や構造は職人さんにお願いするものの外壁や内装は自分たちで作る(ハーフセルフビルド)
・大手の工務店ではなくて、地元の建築家、職人さんに作ってもらう
ということで木を切ったのは2022年の10月〜11月、木が休止期間に入って水を吸い上げるのをやめる秋から冬の時期が湿り気が少ないので、伐採に適しているのだそうです。木を切ると言ってもどのあたりに家を建てたいかをイメージし倒す木を決めて切り倒していきます。密集しているので素直に倒れずに引っかかってしまう木があったり、倒した木が重なって足場がどんどん悪くなって作業性が悪くなっていきます。倒した木は倒れたその位置で枝打ちし、材木にできる太い部分は4.5メートルの長さに、細い部分は2メートルに切ります。2メートルの材はあとで薪にするために取っておきます。こんな作業なので伐木できるのは1日平均4本程度でした。
その後グラップラーを借りてきて製材用の木と薪用の木をそれぞれ土地の端に積み重ねて、やっと地面が見えてきますが、作業はまだ続きます。
根っこを引き抜かないと家が建てられないので、切った木の根をほじって抜きます。根は横に広がる部分と縦に伸びる部分があるので、広く深くパワーショベルを使ってほじくりまくります。
こんなことをしてやっと「地面と空」を手に入れたのが12月でした。この後は冬になり地面が凍るので土地の作業は中断です。伐木は全く初めての経験で、怪我はしなかったもののチェーンソーを壊したり、思わぬ方向に木を倒したりしましたが、森林伐採の経験のある友人に手伝ってもらうことでたどり着けたのでした。
ほぼ同じ頃地元の建築家との打ち合わせが始まりました。住まいかたの希望を伝えレイアウトを検討したり、地元の製材屋さんを教えてもらったり、近くに住んでいる地元の人たちへの挨拶をしたりと、次の右往左往が始まったのでした。
あっ、「地面と空」が手に入ったと言いましたが、まだ2022年12月時点では水道や電気はないんです。その右往左往も次回で紹介したいと思います。
●中間のまとめ
家づくりを始めて思ったことは、設計(士)よりも現場の職人さん達の工夫や技が大切だということを学びました。
クルマデザインのような
【スケッチセレクション⇒スケールモデル⇒フルスケールモデル⇒GW1⇒生産展開⇒試作⇒完成】といったプロセスがなく【打ち合わせ⇒平面図⇒打ち合わせ】を繰り返しある程度固まったところで立面図や建築例を見せてもらいながら仕様を決めたのでした。予算を限ったのでモデルなしでの進捗なのです。土地自体もプロが整地したものでないだけにそれぞれの職人さん達が現場合わせで対応してくれて、マスプロ住宅とは全く違う満足感を得つつ家づくりが進んでいます。
この文章を読まれている方は、「いつ完成なんだ?」と思われていると思います。近所の人(とは言っても100メートル以上離れていますが)からも挨拶の時に聞かれました。
「完成は分かりません多分2年後くらいには落ち着いていると思います」というのが答えです。
ずっといじっているというのも面白いと思っています。
8月末現在で基礎と柱と屋根が乗った状態までたどり着くました。壁の断熱処理が済むと
いよいよ、自分たちによる外壁貼り始まるのですが、手伝ってくださる人募っていますので
ボランティア大歓迎ですので、よろしくお願いします。
ここまで拙文にお付き合いくださりありがとうございます。
次回は設計から引き渡しまでの顛末です。建築士とのやりとりから形になるまでのお話ですが、工務店が間に入って各種調整監督を請け負ってくれる施工形態とは異なる故に色々な事が起きていることを書きたいと思いますので、よろしくお願いします。




